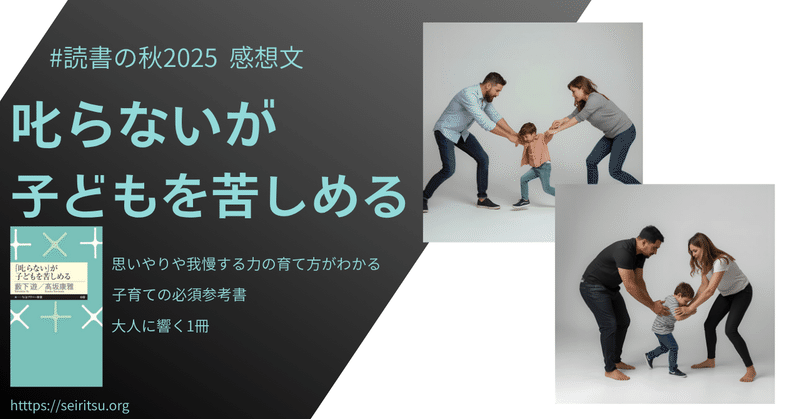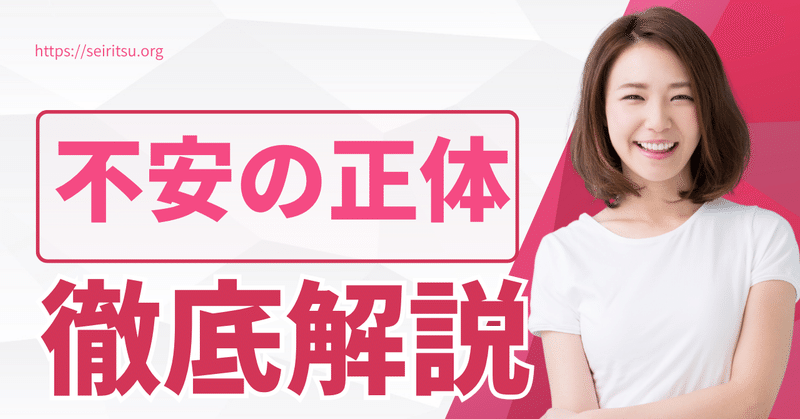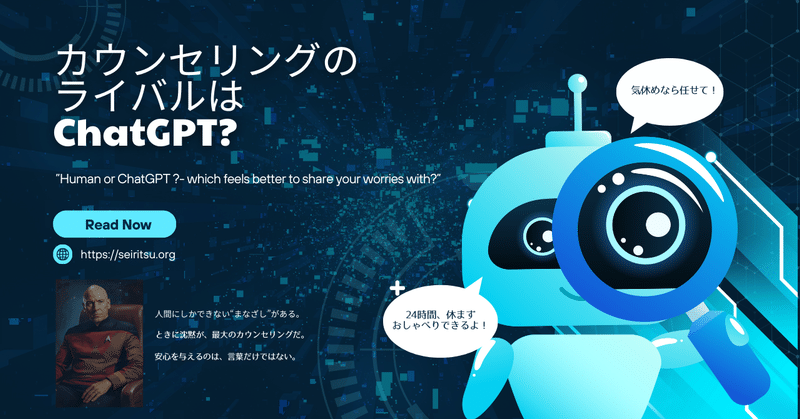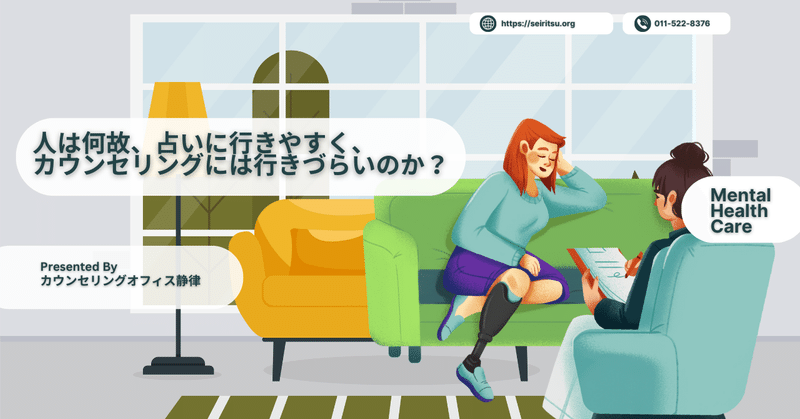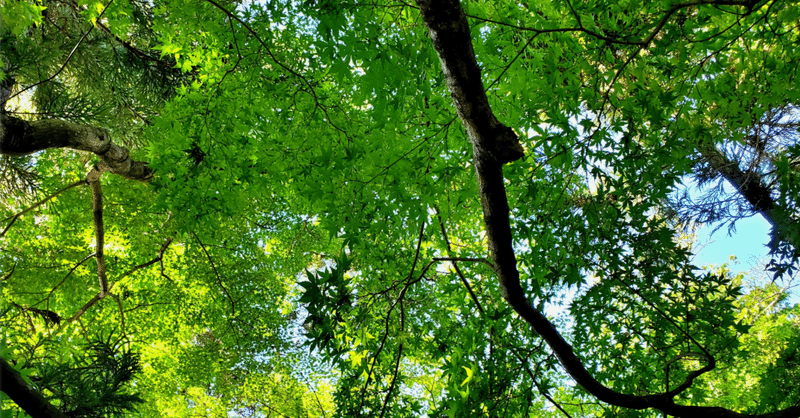自傷行為カウンセリングself-harm counseling
自傷行為(リストカット、頭を打つ、爪を噛む、過食嘔吐など)は、強いストレスや感情のコントロールが難しくなったときに生じることがあります。自傷は一時的な安心感を得るための行動ですが、根本的な問題を解決するものではなく、繰り返すことで心身の負担が増えていく可能性があります。
カウンセリングでは、自傷に至る背景や感情を整理し、より適切なストレス対処法を身につけることで、自傷行為に頼らなくても安心して過ごせる状態を目指します。
自傷行為カウンセリングで相談できること
- リストカット・ピアス開け・頭をぶつける・爪を噛むなどの行為をやめたい
- イライラや不安、つらい気持ちをどう発散すればいいかわからない
- 自分を傷つけることで安心するが、やめたい気持ちもある
- 誰にも相談できず、孤独感がある
- 自傷行為が周囲にバレたくないが、やめる方法を知りたい
基本的なアプローチ
自傷行為のカウンセリングでは、まず本人の気持ちを大切にしながら、行動のパターンやストレス要因を整理し、少しずつ対処法を変えていくサポートを行います。
-
現状の整理と自傷行為の背景の確認(初回セッション:ヒアリング)
- 自傷行為の頻度や状況を整理し、どのようなときに衝動が生じるのかを明確にします。
- 自傷を通じて得ている感覚(安心感・気持ちのリセットなど)を整理します。
- これまでのストレス対処法を振り返り、どのような改善が可能かを考えます。
- 自傷行為が生命の危険を伴う場合は、適切な医療機関との連携を検討します。
-
自傷衝動の理解と対処法の検討(2~3回目:心理教育的介入)
- 衝動が生じる前後の感情や考え方を整理し、トリガーとなる要因を特定します。
- 感情をコントロールするための方法を学びます。(TFT・マインドフルネス・リラクゼーション法など)
- 自傷の代わりにできる行動(クッションを強く握る・冷たい水を触るなど)を一緒に考えます。
- 必要に応じて、認知行動療法(CBT)の手法を取り入れ、考え方のクセを修正します。
-
感情のコントロールとセルフケアの実践(3~5回目:代替案の提案)
- ストレスを適切に処理するための具体的な行動プランを立てます。
- 「自傷しなくても安心できる」状態を目指し、セルフケア方法を増やします。
- 生活リズムを整え、心身の負担を軽減する習慣を取り入れます。
- サポートを受けられる環境(家族・友人・支援機関など)を一緒に考えます。
-
フォローアップ・継続的なサポート(6回目以降)
- 自傷行為の頻度や衝動の強さの変化を確認し、必要に応じて対策を調整します。
- 「つらくなったときの対処法」を振り返り、自分に合った方法を定着させます。
- 自分の気持ちを適切に表現できるようサポートを続けます。
- 長期的にストレスをコントロールしながら、自分らしく過ごせる環境を整えます。
- 長期的なセルフケアの方法を見つけます。(趣味・運動・リラクゼーション)
- 落ち込みが続いたときの対処法を準備します。(セルフコンパッション・コーピングプラン)